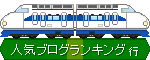Contents
※この記事にはプロモーションが含まれています。
給料が安いイメージの介護職。
「一人暮らしできるくらい月給はもらえるのだろうか?」と不安に思う人もいるかもしれません。
結論から言うと
介護職でも一人暮らしは問題なく可能です。
厚生労働省が公表している介護従事者処遇状況等調査によれば
介護士として働いている介護福祉士の
平均給与額はおよそ30万円
賞与も含めれば年収400万を超えるくらいになります。
とは言えこの数値は、管理職やベテランも含めてた額面の給与で
若手、中堅の介護士が実際に手に入る所得としてはもっと低い数字にはなります。
それでも中規模以上の介護施設であれば
手取り20万近くの金額は得られます。
賞与も合わせて年収およそ350万くらい。
なので介護士でも一人暮らしは不自由なくできるし
貯蓄も可能なレベルです。
ちなみに日本の20代前半年収の中央値は
250万(賃金構造基本統計調査より)。
介護職の給与水準は高くありませんが、
実は低すぎるということもないのです。
ではここで私が働いた施設の入所介護、通所介護の給与額の詳細を紹介していきます。
介護職に就こう、転職しようと考えている方に参考になったら嬉しいです。
東京郊外の介護施設 事例 入所介護介護福祉士の給与・年収

入所介護の給与額
2020年私の年収は約400万でした。月に夜勤を6〜7回入ってこれくらいの額です。
2021は適応障害で休職を1ヶ月、半年間夜勤なしで約340万でした。
残業時間はほぼゼロでのこの金額。
拘束時間は長くないのでプライベートな時間を確保しつつ年収350万くらいを維持できるので底辺といわれるほどの大変さではないのかなと個人的には思っています。
むしろ子育てにも力を入れたい男女におすすめできるくらい。
月の内訳はこんな感じです。
基本給 180,000円+年昇給(1,000円)
介護処遇加算 27,000円 事業所の加算状況や稼働率で変動します。(特定介護処遇加算も込み)
資格手当 10,000円 介護福祉士持っていると手当がつきます。ケアマネ資格も取ると更に+5000円アップ。
夜勤手当 36,000円 1回6,000円で月平均夜勤が6回あります。
早番遅番手当 3,000円 1回あたり500円の手当がもらえます。
住宅手当15000円 世帯主が「本人」での金額です。
調整手当 10,000円 子供の扶養手当です。1人増えるごとに+5,000円されます。
通勤手当 4,100円 私の勤め先は、自転車通勤4km以上だと通勤手当が支給されます。
税金が引かれると手取りで20万〜22万円くらい。
さらに7月と12月は賞与が支給されます。(2020年、2021年は基本給の3.0ヶ月分支給)
自転車の保険、拠出年金(月9,000円)も会社が負担してくれているので額面の数字より手厚い印象です。
介護施設で働くメリット
・大枠のルーティーンが決まっているので慣れてさえしまえば仕事の難易度は高くない
・不況に影響されにくい
・職場の雰囲気がゆるめ(切磋琢磨のピリピリ感はない)
・自転車で通勤可能な範囲を探しやすく、余暇時間を得やすい
介護士の仕事内容は体力勝負なところもありますが、慣れて力の抜き所さえ掴めてしまえば苦にならないと思います。 周りの職員との相性が良ければ精神的な負担が少なくて済みます。
通勤もほとんどの職員が自宅の近場を選択します。私は自転車通勤なのでストレスゼロ。毎日満員電車に乗らなくて良いのは本当に楽です。
そして日本は超高齢化社会というだけあってコロナ禍においても引く手はごまんとあります。現状すぐに職を失う心配はほぼありません。安心して働くことができます。
介護施設で働くデメリット
・夜勤がきつい
・早番、日勤、遅番、夜勤の勤務があるため生活リズムが整いにくい
・介護技術を磨いても将来の年収アップには繋がりにくい
夜勤手当はあるものの月に6回以上夜勤業務があるのは体への負担は大きいです。
ただ、夜勤は黙々と自分のペースで働けるので個人的には楽しい業務です。
シフト制の勤務なので体調を崩すとなかなかリズムを取り戻せないのも欠点ですね…。
あと介護技術をいくら高めたとしても給与・年収面でのアップは難しいです。
どう頑張っても技術次第で「3人同時にオムツ交換ができる」ようになる訳ではないので個人の生産性が高まり辛い仕事ではあります。
Thoughts
介護職の魅力は、「雇用の安定」と「余暇時間」を得られることです。
周りとガツガツ競走していく風土ではないので心穏やかに自分のペースで生活しやすいのも利点。
反面、高年収の機会損失や健康管理が大変になってきてはしまいますが、
それを差し引いても精神的な負担が少なくて介護職は個人的に魅力ある穴場的な業種だと考えています。
関連記事
HSPの現実的な適職を紹介!〜介護職の働きやすさを現役介護福祉士が徹底解説〜
夜勤がなくても一人暮らしは問題ない 通所介護(デイケア) 介護福祉士の給与・年収
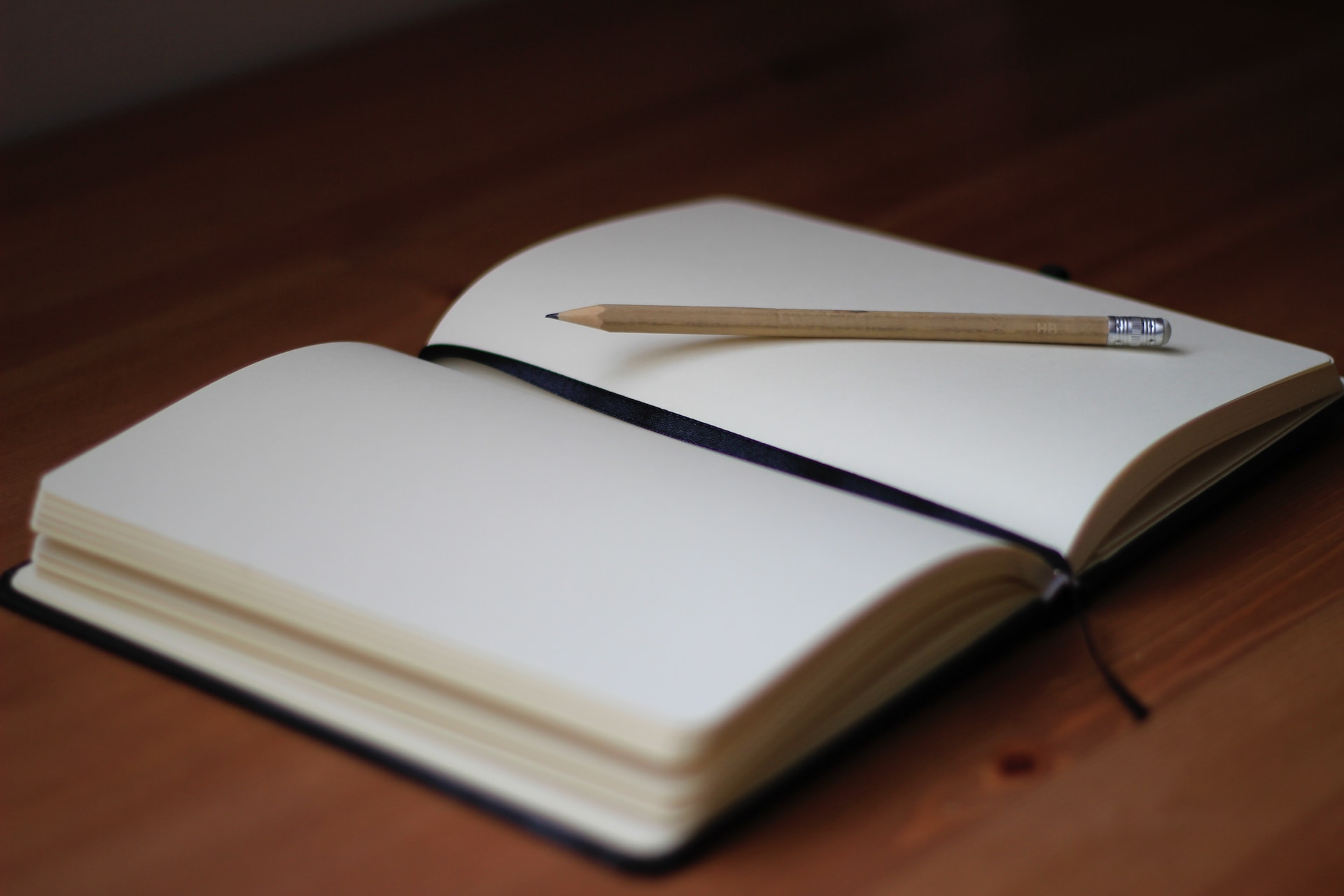
年収は大体270万前後。
ただし通所介護は正社員ではなくフルタイムパートとしての給与額になります。
正社員だと賞与額が多くなるので300万は越えられると思います。
介護求人は数多くあますが、通所介護の正社員採用は案外少なくてパート雇用が多いです。
かくいう私もデイケアで働いていた時期はパート契約でした。
小さいお子さんのいる方は拘束時間が1〜2時間短くなるパート契約の方が働きやすいかもしれません。
通所介護の給与額(フルタイムパート)
基本給 17,3000円 時給が1,030円×22日で計算しています。介護福祉士の資格ありでこの時給です。無資格だと980円です。
介護処遇加算 35,200円(※特定介護処遇加算なし)
時間外手当 5,000円
税金、食事代で4.5万ほど引かれて手取り18万円くらいです。
パートでしたが6月と12月に各10万くらいの賞与をもらえていました。
各事業所によって介護処遇加算でもらえる金額はかなり変わってきます。
手取りは一人暮らしだとやや余裕のない金額ではありますが、不自由なく生活できる水準ではあります。
通所介護で働くメリット
・朝〜夕までの仕事なので生活のリズムが作りやすい
・丁寧に仕事をした分だけ利用者さんに感謝してもらえる
・営業ノルマ的なものはないので精神的に疲弊せず仕事ができる
デイケアで働いていると利用者さんの声をダイレクトに受け取れるので働き甲斐があります。失敗して落ち込むこともありますが創意工夫の余地があるのでモチベーションを保ちやすいです。
勤務時間帯は8時30分〜17時30分で生活サイクルが整いやすいのもありがたい利点。
一般企業勤めの方より断然健康的な生活が遅れます!
通所介護で働くデメリット
・リハビリ計画書や行事の準備のために残業をすることが多い
・夜勤がない分手取りがどうしても低い
・利用者さんの滞在時間が限られているので一日の業務が目まぐるしい
難点は1日のスケジュールがタイトなところでしょうか。
1日で60~70名くらいの利用者さんが過ごされていたのでトイレやお風呂が混雑しやすいです。午前中だけで50名以上の入浴介助を実施していました。そのおかげでいつもバタバタ…。
あと毎月行事があり準備のための残業がやや多めでしたね。
夜勤業務がない分、入所介護と比べると数万円給与額は少なくなってしまうのも痛いところ。
Toughts
デイケアのような通所介護は明るくてコミュニケーションが上手い人ではないと務まらなそう…。
そう思われる方もいると思いますが、口下手な真面目タイプの私にも務まるくらいなので介護士にコニュニケーション力はそこまで重要ではないです。
利用者さんを真摯に対応する。
口下手でも職員の輪に入る努力をする。
これらを心掛けていれば自然と周りに受け入れてもらるようになるものです。
通所介護は介護職の中でも特に挑戦しやすい仕事です。
女性が多い職場で競い合う雰囲気がないのが魅力。
新卒で社会人生活を挫折した私にはこころのリハビリにもなりました。
「働くことって楽しいことでもあるんだな」と気づかせてくれた仕事です。
関連記事
高齢者施設で実用的な介護士にも負担が少ないレクリエーション -人前に出るのが苦手な人向け-
給与・年収の低い介護職でもちゃんと一人暮らし生活は送れるの?

給与が低いイメージの強い介護職・介護福祉士。
実際に介護士として働いている私さといものリアルな貯金事情を紹介します。
正社員6年、フルタイムパート4年の約10年間で1,000万円貯蓄できています。
その間に「うつ状態」や「適応障害」を患いもしましたが介護職でこの金額が貯まりました。
手取りでが20万前後あれば充分に普通の生活が送れます。前途していますが問題なく一人暮らしできる水準。
特別副業でお金稼ぎをする必要がないくらい。
なので、給与が低い介護職でもちゃんとした生活は問題なく送れます。
むしろ貯金もどんどん積み立てられるくらい。
「何に対してどのくらいお金を使っているのか」を把握、管理さえできれば月8~10万円の貯蓄積み立ては無理なくできます。
なので皆さん安心して介護職にいらしてくださいね。
介護士さといもが実践している薄給対策
とは言え介護職の給与が他職種に比べ低い水準なのも事実。
なので不必要な支出を減らして薄給を補う考えは大事。
私さといもが実践している対策を紹介します。

①断砂利
使わなくなったものはすぐに売るか捨てるかします。
「まだ使うかもしれないし…」と取って置くことは基本的にしません。
家のスペースを圧迫しないし、お金の節約にもなるからです。
お気に入りだったものでも飽きたのなら売る。
この判断基準を設けることは節約にとても有効です。
なぜならその決断が早ければ早いほど売却価値は高くなるから。
さといもの大好きなゲームの話で例えるなら、
新品のソフトを7,000円で購入→1〜2ヶ月遊ぶ→買取店へ行き3,000円で売る
これなら実質4000円の負担。新品を半値で購入したようなものです。
「まだ使うかも…」と持ち続けてしまうとこのキャッシュバックをどんどん減額されていってしまいます。
メルカリなどを使えば高値で売れるようですが、
私は手間隙が惜しいのでブックオフなどの大手に買い取ってもらいます。手間より楽を優先。
ブランド品も同様です。
1年以上使わないならこの先もきっと出番はありません。
さっさと売ってそこで得たお金を新しいものに充ててしまえば良いのです。
②もらえる生活必需品はもらう
生活において使用頻度が高いものは積極的にもらいます。
断砂利と矛盾しているようにも見えますが、「やっぱいらないな」と思ったら破棄すれば良いのです。
今まで私がもらった大きなもの
・車
義両親が「車を買い替える!」とのことで古い車を譲っていただきました。
車年数は7年くらいなのでまだまだ現役として使ってます。
・電動自転車
義理のお姉さんの娘が小学校に上がるというタイミングで譲ってもらいました。
息子の保育園送り迎えに重宝しています。
・ソファ
実家で物置と化していたものをもらいました。
寝っ転がれるし足も伸ばせて本も読める感じのものなので快適に使えています。
テーブル(こたつ付き))
実家に「いつか使うかもしれない」と物置で埃かぶっていたテーブルももらいました。
お古なので「汚れてもいっか」と安心して使えます。2歳の息子が傷をつけたってヘッチャラです!
・棚や突っ張り棒
兄が引っ越した際にいらなくなったものをもらいました。しっかりした物買おうとすると意外とお高い突っ張り棒。
このように こだわらなければ家具や家電の費用はグッと下がります。
そして、身近な人から譲り受けるものは使い勝手もわかっているものが多いから無駄になりにくいのも利点です。

③身を置く環境
自分が何処に住んでどんな人と暮らして、どんなコミニティー所属しているかは「貯める力」にかなり影響します。
私は介護士なので都心や駅近なとこに住むメリットはあまりありません。なので郊外の家賃7万3千円の2LDKアパートに住んでいます。
家族4人暮らしでも十分快適に過ごせています。
職場も自転車で20分くらい。
そしてなによりも大きいと感じるのがパートナーである妻が浪費をほとんどしない。
私はもともと浪費をしない質なのですが、彼女は私以上に物を買わない。
新しい高級バックや財布が欲しいと聞いたことがありません。
その影響で私も物欲がかなり減り無駄なものを買う習慣が激減しました。
④高級ブランドを買わない
20代の頃は不相応にもグッチの財布やバーバリーのコートなんかを買ってしまっていました。
確かに買った瞬間はものすごく嬉しい。でも嬉しさの長続きはしません。
お洒落だけれど使い勝手があまりよくなかったり、ブランドに特別な思い入れがあるわけでもないし1年も過ぎれば飽きてしまいます。
実際に買って使ってみてから気づいたことではありますがこだわりがなけれは高級ブランドは必要ないなと感じます。
それに子育てしていると食べこぼしや砂にまみれて高級な服なんて着ていられません。
機能性重視で洗いやすいコスパに優れた服へ自然と移行していきます。
⑤ふるさと納税の活用
ふるさと納税は一般企業に勤める人にとって数少ない節税です。
数千円〜数万円の寄付を自治体に寄付し2,000円の負担(複数の自治体に寄付しても2,000円で済みます)で返礼品がもらえます。
収入によって免除される納税額が変わってきます。※「さとふる」や「楽天」でシュミレーションできます。
「それの一体どこが節税になるの?」と疑問に思う方も多いかもしれません。
具体例はこんな感じ、
〇〇市に10,000円を寄付した場合は、2000円以上相当の返礼品が〇〇市受け取れる+翌年の市民税が8000円控除される。
寄付をした10,000円に対して、控除額+返礼品の合計額が実質10,000円以上になるので
結果的に実際に寄付をした額よりも数千円〜数万円の得をする。
これをみんな「節税」と呼んでいるわけです。
自治体によってはお米や水、オムツなんかもありますので日用品を返礼品として選ぶこともできます。
確定申告が面倒と思われる方には「ワンストップ特例制度」というものもあります。
これは寄付した自治体が5つ以内の時に使える制度で自分で確定申告をせずに自治体から送られてくる書類を数枚(大体2枚)記入し自治体に送るだけで控除を受けられる制度です。
書類も簡単なものになっていますので便利ですよ。私さといもも活用しています。
※要注意なのは自分自身で確定申告を行う方は「ワンストップ特例制度は使えません!
医療費控除など個人で確定申告をする時はふるさと納税の確定申告も自分で行うことになります(寄付金控除)。
このような感じでコツコツ無駄を削っていくことで貯蓄を積み立てられることができますよ。
関連記事
『HSPが働きやすい介護職』現役介護福祉士が厳選!! 金銭的に役立つ資格
「仕事ができない」と感じる理由 HSPの社会生活体験談を調査まとめ